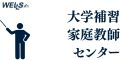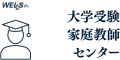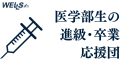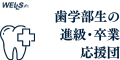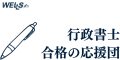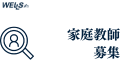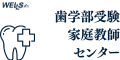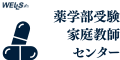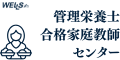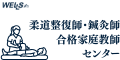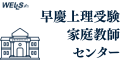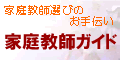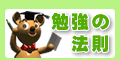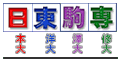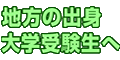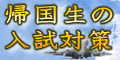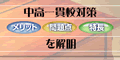行政書士試験の最重要科目、行政法を攻略せよ― 得点の「核」を作り、合格を最短でつかむ ―

行政書士試験の合否を左右する最大の科目、それが行政法です。
全60問中19問、配点は76点(全体の約4分の1)。
ここで得点できるかどうかが、合格ラインを超えられるかを決めます。
(出典:アガルート行政書士講座 出題分析、伊藤塾コラム)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出題数 | 19問(択一・多肢・記述含む) |
| 配点 | 76点(記述2問×20点を含む) |
| 主な範囲 | 行政法総論・手続法・不服審査法・訴訟法・地方自治法 |
条文だけでなく、「制度の目的」と「判例の理由」が理解できているかが問われます。
つまり、“覚える”より“考える”科目。だからこそ差がつきやすいのです。
行政法で得点を伸ばすための考え方
東京大学教育学研究科レビュー(2012)では、
「法学の理解は構造化学習(条文・趣旨・事例の関係づけ)によって深まる」とされています。
行政法も同様に、“つながり”を意識した学びが得点アップのカギです。
過去問を徹底的に分析する
行政法は出題傾向が非常に安定しています。
神戸大学のレビュー(2023)によると、
「過去問演習を中心とした反復学習が、理解の深化と成績向上に最も効果的」だとされています。
まずは過去3〜5年分を繰り返し解き、問われ方の“型”を体で覚えましょう。
条文と判例は「背景」から理解する
文部科学省の報告(2024)では、
「法制度を目的や背景とともに学ぶと、単純暗記より長期記憶に残る」と指摘されています。
たとえば「行政行為の取消」を学ぶときは、
- 誰が(行政庁)
- どのような目的で(公益・適法性)
- どんな手続で(通知・不服申立)
を整理して理解すると、応用が利くようになります。
記述式は“早めの慣れ”がカギ
記述問題(20点×2問)は、行政法の理解を文章化できるかどうかを問う形式です。
東京大学の実践研究では、「定期的な論述訓練を行う学習群は、非訓練群に比べ法的思考力が有意に向上した」と報告されています。
まずは過去問の模範解答を“写してみる”ことから始めましょう。
文章構成のパターンが自然と身につきます。
制限時間を意識して演習する
行政法は文章量が多いため、時間配分も勝負の分かれ目です。
演習時から1問あたり4〜5分を目安に、
「設問→肢→判断根拠」の順に処理する練習を重ねておくと、本番で落ち着いて対応できます。
ウェルズの考え方:行政法を「武器」にする
行政法は、努力が結果に直結する科目です。
暗記中心の学習では伸び悩みますが、構造的に理解すれば得点が安定します。
ウェルズ家庭教師センターでは、
- 条文・趣旨・事例をつなげて理解する「三層構造学習」
- 判例の“背景と理由”を言語化するトレーニング
- 記述と過去問分析を融合した「実戦型指導」
を軸に、短期間で確実に成果を出すプランを提供しています。
入会金は33,000円(税込)、月謝制のみで追加費用は一切なし。
まずは無料体験で、「行政法を得点源に変える学び方」を体感してください。
参考・出典一覧
- 神戸大学「個別学習支援と学力成果の関連分析」
https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/81008398/81008398.pdf - アガルート行政書士講座「出題分析」
https://www.agaroot.jp/gyosei/column/exam_subject/ - 伊藤塾コラム「行政法攻略のポイント」
https://column.itojuku.co.jp/gyosei/method/gyoseihou/ - 東京大学 教育学研究科レビュー「学校外教育の動向と成果」
https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/30951/files/edu_55_05.pdf - 文部科学省「教育実証研究報告(2024)」
https://www.mext.go.jp/content/20240617-mxt_kyokasyo01-000035395_4.pdf
お問い合わせ
無料体験のご依頼や、大学生活でのご相談、その他ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください
フォームでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
受付時間 10:00~18:00
(土日祝日、年末年始、夏季休業日を除く)